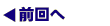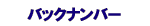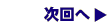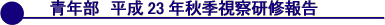
今回の研修は、【1日目】滋賀県坂本にて石積み技法「穴太衆積み」の講義を受け、【2日目】彦根城の石積みと滋賀の庭園を視察、【3日目】京都の庭園を視察、という内容で行なわれました。
【1日目】
研修初日、まず滋賀県は比叡山の足元、坂本にある粟田純司氏(文化財石垣保存技術協議会会長、(株)粟田建設会長)の元へおうかがいし、「穴太衆積み」の講義を受けました。「穴太衆」とは、主に戦国時代以降、城郭の石積みで全国的に名を馳せた石工の技術者集団で、その石積みの堅固さより、多くの城の石積みが穴太衆の指揮の下で作られたといいます。㈱粟田建設ではその技術を今に継承し、多くの城の石積みの整備・復元に携わっています。
講義は穴太衆の起源から始まり、時代による石積みの変遷、その後穴太衆積の積み方や特徴に関して資料を見ながら学びました。

講義の様子
その後は外に出て石積みの多く残る坂本の町並みを歩き、実際にいろいろな石積みを見ながら講義を受けました。

歩きながらの講義

坂本の町並み
坂本の町には本当に石積みが多く、歴史を積み重ねた風情があります。
最後に粟田会長が石積みの極意を語ってくれました。それは「石の声を聴き、石の行きたいところへ持っていく」こと。長い修練・経験を積み重ねることでしか体得できない伝統の技術と感じました。
【2日目】
翌日は朝一番に「彦根城」を視察。参加者みな前日の講義の内容を思い出しながら、注意深く城の石積みを観察していました。

彦根城の石積み

左右で異なる積み方

岩につぎ足してある

増築部分
また同時に、庭園「玄宮園」も視察しました。
ここは彦根城の天守そのものを借景に用いた池泉回遊式の大名庭園で、滋賀8箇所の名勝、近江八景の縮景園でもあります。この日は晴天に恵まれ風も無かったので、彦根城の天守が池に映りこみ、美しい眺めとなっています。

玄宮園

西明寺
その後は「西明寺」、「金剛輪寺」、「百済寺」を視察しました。この3つの寺院は歴史も古く、琵琶湖の東にあるため湖東三山と呼ばれて親しまれており、また紅葉の名所としても広く知られています。

金剛輪寺

百済寺
そして2日目の最後は「石山寺」を視察。巨大な岩を割って生えるモミジが見所の、紫式部ゆかりの寺院です。

石山寺
【3日目】
最終日は京都の庭園を視察しました。まずは右京区花園の妙心寺に向かい、その中で多くの寺院を視察しました。妙心寺の広い境内の中には多くの塔頭寺院があり、今回の研修では、常時拝観可能な寺院と、秋の特別拝観で公開される寺院をすべて視察しました。

退蔵院
まず塔頭のひとつ「退蔵院」へ。美しい庭園がある常時拝観可能な寺院です。藤棚下のベンチに腰掛け、奥行きのある庭園を眺めて朝一番の清清しさを感じます。
そのまま「大法院」へ。ここでは庭を眺めながらお茶をいただけます。このお茶、けっこうな人気があるようで、朝から早くも人が増え始めている様子でした。ほっと一息、心を落ち着けて何かに思いをめぐらせる。そんな時間がありました。

大法院

麟祥院
次は「麟祥院」。秋の特別拝観ということで入ることができました。中ではガイドさんから、ふすまに描かれた雲龍図や椿屏風、方丈庭園などの説明を受けることができました。残念ながら庭園内での撮影は禁止されていたため、門の外からの写真です。

妙心寺方丈

大心院
次の「大心院」では、白砂と青苔が美しい、いかにも禅宗らしい風格のある枯山水を視察。
「桂春院」ここも秋の特別拝観ということで入ることができました。縁側に腰掛け、静寂の中に落ち着く紅葉の風情を味わいます。

桂春院

仁和寺

龍安寺
最後に集合写真を。参加された皆様お疲れさまでした。