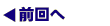 |
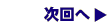 |
樹木医からの一言(18)
土壌の三相分布について
・ 土壌は、固体、液体、気体の三部 分によって構成され、
それぞれを固相、液相、気相という。
これら三相を容積百分率で表示したものを三相分布あるいは
三相組成と呼んでいる。
・ 固相は、砂、シルト、粘土などさまざまな形態、粒径、化
学組成の無機鉱物と有機物から成り立っている。
・ 液相は孔隙と呼ばれる固相間のすき間の一部を満たす土壌
水であり、固相との結びつきの強さによって重力水、毛管水、
膨張水、吸湿水の順に区別される。重力水は固相との結びつ
きが最も弱く、0.1㎜以上の大きさを持つ固相間のすき間に存
在する液相で、排水性を判断する場合に重要な指標となる。
・ 気相は孔隙のうち、土壌水で満たされていない空間部分を
いう。湿害は気相率不足に原因しており、気相率は少なくとも
20%以上は必要とされている。
・ 液相や気相の比率は、土壌の水分状態などで変化するが、
固相率は地質や母体でほぼ一定の値となる。火山灰土は16〜30
%と低く、非火山灰土では40〜45%が一般的な値である。
・ 三相分布は、土壌粒子と水の充填状態を総合的に表示して
いる。すなわち、固相率は土壌の硬さと関係し、気相率は通
気性や排水性と関係しており、生育、特に根の伸長と密接に
関連している。
・ 一般的には三相分布の理想的な比率は、固相:液相:気相
が5:2:3、あるいは5:3:2といわれている。
・ 一般的には固相率が高くなったために三相分布が問題とな
ることが多い。その対策は、深耕、心土破砕などにより
ち密層を膨軟化させることが必要である。