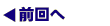 |
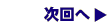 |
樹木医からの一言(10)
「マツ枯れ」について その2
―穿孔性甲虫類と樹木―
・主としてキクイムシ科、ゾウムシ科、カミキリムシ科に分
類され、樹皮下に孔を開け、坑道を穿つ。これらの昆虫は、
材やそこに繁殖する菌類を餌にしている。
・ 樹木の旺盛な防御反応を突破して健全な木(生立木)を加
害する害虫を一次性害虫(スギカミキリ等)と呼び、他の
原因で衰弱した木や伐倒木のように、防御反応が低下した
樹体しか加害できない害虫を二次性害虫と呼ぶ。大部分の
穿孔性昆虫は二次性害虫である。
・ 樹木の材は、セルロースとヘミセルロース、リグニンと呼
ばれる三つの高分子物質から構成されている。これらはい
ずれも、生物が消化・分解しにくいうえ、ほとんど窒素が
含まれていない。窒素は、生命活動に不可欠のタンパク質
の構成要素である。
・ 炭素と窒素の比率はC/N比と呼ばれ、一般にこの値が小さ
いものほど、すなわち窒素の割合が高いものほど、食物資
源として質が高いと評価される。
・ 材の中には、炭素源は有り余るほどあるが、窒素は少しし
か存在しない。このため樹幹を攻撃する害虫といえども、
材だけを食餌源にしていては生きていけない。
・ 穿孔性甲虫類のうち「樹皮下甲虫類」(バークビートル)
は、内樹皮という形成層を含む生きた組織を主に摂食する
ことにより栄養を充たしている。この組織は細胞質をたっ
ぷり含んだ生細胞からなるため、樹木組織では珍しく、栄
養分に富んでいる。
・ 一方樹木は、忌避作用や毒作用のあるモノテルペン類等の
精油成分や、タンニン、ポリフェノールなどを蓄積して害
虫の攻撃に抵抗している。なかでも針葉樹の場合、有効な
防御手段は樹脂(やに)の分泌である。
・ 樹皮下昆虫の幼虫が樹皮部を食害していくと樹脂に取り囲
まれ、大部分の幼虫は死んでしまう。