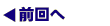 |
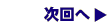 |
樹木医からの一言(11)
「マツ枯れ」について その3
―穿孔性甲虫類と樹木―
・ 一次性害虫のあるグループは樹木の抵抗性を打破
するため、多数の成虫が同時に樹幹の特定の部位
を集中攻撃する「マスアタック」という戦略を発達
させた。マスアタックを可能にしているのが集合
フェロモンという信号物質である。
・ マスアタックを受けると、樹木の方では防御用の
樹脂が枯渇してしまい抵抗力を失うので、キクイ
ムシの幼虫は危険にさらされることなく、樹皮下
の栄養分豊かな形成層付近を食害できる。
・ 二次性害虫である大部分の樹皮下キクイムシは本
来マスアタックの習性は持たないが、風害や食葉
性昆虫の大発生などで衰弱木が大量に発生する
と、その上で個体数を急増させ、結果的に周辺の健
全木にマスアタックすることになる。これが「二次
性害虫の一次性害虫への転化」である。
・ また、樹木の抵抗力を封殺するために、病原性のあ
る青変菌類と共同歩調をとることがある。青変菌
とは、樹木の辺材部を侵し、材を青黒く変色させる
一群の子嚢菌類のことである。
・ これらの菌は侵入部周辺の生きた樹木組織を殺
し、辺材部に侵入し一か月程で辺材部に広がり、水
の通導を止めさせ樹を衰弱させ、抵抗反応を抑え
込む。
・ 多くの穿孔性甲虫類は、材の中で例外的に栄養分
に富んだ樹皮下の組織を利用している。いわゆる
樹皮下昆虫である。しかし材のこの部位は競争者
が多く、また樹皮直下であるため外部からの寄生
性昆虫の攻撃にもさらされやすい。
・ もっと材内深くに潜り込んで生活できれば安全こ
の上ないが、窒素分の枯渇という問題がある。
・ 腐朽材を利用する昆虫達が、材と微生物の混食と
いう方法でこの問題を克服しているが、腐朽材は
競争者や天敵が多いニッチェでもある。