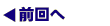 |
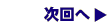 |
樹木医からの一言(12)
「マツ枯れ」について その4
―穿孔性甲虫類と樹木―
・ マツ枯れに関与している可能性のある昆虫として、四種の
キクイムシ、三種のゾウムシ、マツノマダラカミキリの計
八種が重要害虫として挙げられたが、実験の結果は、これ
らの害虫には一次性害虫の能力がないことを強く示唆する
ものであった。
・ 枯死したマツの材中から線虫が発見されたが、この線虫は
ブルサフェレンクス属の線虫で、九州の各地の被害木から
検出され、マツの根幹枝に寄生しており、各組織の靭皮部
や木質部の仮導管、樹脂溝、髄線中に発見される。
・ 病原体である線虫がマツ樹体に侵入後、侵入部位以外から
はほとんど分離できないほどその数が低密度であるうちに
すでにマツを発病させ、松ヤニ分泌が異常になる。病徴が
驚異的な速度で進行する。
・ 昆虫の気管系の開口部は「気門」と呼ばれ、胸部に二対、
腹部に八対あるのが原則であるが、マツノマダラカミキリ
の場合は、腹部には七対。
・ マツノザイセンチュウは、腹部の最も前に位置する腹部第
一気門と、二対の胸部気門を主たる入り口として、その気
管系内に侵入する。
・ 気管系の内部に侵入する線虫は、耐久型(分散型第四期)
幼虫と呼ばれる特殊ステージになっており、まったく栄養
摂取しない「静止状態」にある。つまり、カミキリを移動
のための手段として利用している。
・ 一頭のカミキリの虫体に、多い場合には二〇数万頭といっ
た高密度の線虫が潜んでいることがある。これらの線虫は
その気管内で、すべて頭部をカミキリ虫体の内部に向けて
いる。