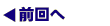 |
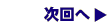 |
樹木医からの一言(13)
「マツ枯れ」について その5
―穿孔性甲虫類と樹木―
・ 健全なマツ樹にマツノザイセンチュウが侵入できる門戸は、
摂食痕しかない。産卵は、すでに発病したマツ樹にしかで
きないので産卵痕ではない。
・ 昆虫の中には、羽化して成虫になった後はほとんど摂食し
ない種類が多い(繁殖活動に専念)。マツノマダラカミキ
リは成虫になった後も、盛んにマツ類の若枝の樹皮をむさ
ぼり食う。このような、成虫が行う摂食行動を「後食」と
呼ぶ。
・ 羽化後もさかんに若枝の樹皮を摂食し続けることにより、
初めて生殖線が成熟し、次世代を残すことができる。
・ 摂食中のマツノマダラカミキリの気門から出てきた多数の
線虫がカミキリ体表を移動し、やがてその尾端に白い塊状
に集合し、摂食しているカミキリの尾端がマツの若枝の表
面に触れると食痕の上にこの線虫の塊が塗り付けられる。
・ 毎年五月から七月にかけて、前年度に枯死したマツ材から
マツノマダラカミキリが羽化脱出してくる。このとき、そ
の体内には多数のマツノザイセンチュウを宿している。こ
のようなカミキリは成虫とはいえまだ生殖腺(卵巣や精巣)
が成熟しておらず、羽化後も健全マツの栄養分豊かな若枝
の皮を喰い続けて性的に成熟しなくてはならない。
・ カミキリの気管系に潜んでいた多数の線虫は、マツの若枝
につけられた後食痕へと乗り移り、マツの樹体内に侵入す
る。侵入したマツノザイセンチュウは樹体内に広がり、や
がてマツ樹は発病する。
・ 林内で性的に成熟した雌雄のカミキリはこのような発病マ
ツに誘引され、幹の上で交尾、産卵し次世代を残す。やが
て、夏の高温と乾燥期を経て病徴は一段と進み、夏の終わ
りから秋にかけて針葉の色は黄色から赤褐色へと変化し、
木は枯死する。
・ この頃、樹体内でマツノザイセンチュウは大増殖し、材片
一グラム当たり数千から二〜三万頭のレベルまで密度を増
す。一方、樹皮の下に産みつけられた伝播者カミキリの卵
は一週間ほどで孵化し一齢幼虫となる。さらに、樹皮下の
組織や材を旺盛に摂食しながら一齢から二齢、三齢へと脱
皮を繰り返し、成長していく。
・ 秋口になると、樹皮下と材を行き来していた幼虫は四齢幼
虫となって材深く穴を穿ち、その穴の入り口に材の喰い滓
の栓をして越冬の準備をする。
・ 翌春、気温が上がると再びカミキリ幼虫は成長を開始し、
やがて五月頃には蛹へと変態する。約二週間ほどで、蛹の
時期を終えたカミキリが羽化するころには、マツ樹はすっ
かり枯損してしまっている。
・ 新しく羽化した成虫たちが後食を始めると、また新たな感
染サイクルが動き出す