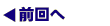 |
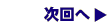 |
樹木医からの一言(9)
「マツ枯れ」について その1
・二〇〇〇・三〇〇〇年前頃に稲作が始まり、食料・生活の
安定と共に人口が増加、周辺森林の開墾・破壊が始まる。
・花粉分析によると、アカマツ・クロマツが増加してくるの
は約一五〇〇年前頃からであり、山地の斜面などの森林を
伐採、焼き畑農耕(雑穀類、マメ・イモ類等)が進行、数
年の栽培活動の後放棄、荒れ地となりアカマツの急速な侵
入をもたらす。
・アカマツやクロマツは細根の部分に菌類が共生する「菌根」
を形成することによって、養分の少ない土地に生育できる
樹種である。
・植生の中で優占するようになるのは五〇〇年前頃(室町・
戦国時代)である。二毛作が普及し、農業が大いに発達し
た時代である。これらの社会的変革が、薪や堆肥にする落
ち葉を採集するなど、森林からの収奪を促してアカマツの
生育適地を作りだし、その優占をもたらす背景となった。
・ところが土壌が富栄養化すると、雑菌がはびこり、菌根菌
が衰弱し、養・水分をめぐる競争で広葉樹に後れをとる。
・荒れ地に先駆的に侵入したマツ類は、人手が入らなければ
次第に広葉樹等に置き換わり、やがて照葉樹林のような極
相林に移り変わる。この現象を遷移と呼ぶ。
・幕藩体制が整う一七世紀以来、海岸の砂防事業が各地で進
められ、これによりクロマツの人工林が次第に日本の海岸
保安林を形成した。
・「マツ枯れ」の最初の記録は、明治三八年(一九〇五年)、
長崎市周辺で調査した資料による。同時期に福岡県でも被
害が発生、数年後鹿児島県の吹上浜、大正三・四年(一九
一四・一九一五年)頃には本州に飛び火。
・太平洋戦争中の森林の荒廃は甚だしく、戦後の被害の急増
をもたらす温床となった。戦時中は、軍事施設を望む周辺
マツ林への立ち入りを厳しく制限したことにより、発生源
をみすみす温存することになった。
・戦中戦後、大量のマツ丸太の移動にまぎれて被害材が搬送
されたため、戦後「マツ枯れ」は九州、中国、四国、近畿
から関東におよぶ二七都府県に広がり、その被害量も七二
万立方メートルに達する。
・戦後、ことの深刻さに連合軍最高司令部は、防除法を勧告。
絶対的権限を背景に林野庁は強力な防除行政を断行。被害
木を伐倒、その皮を剥ぎ焼却。その効果は顕著であり、被
害は急速に鎮静化。理由は駆除作業を徹底したこと、労働
力が充分に確保できたこと、枯れマツが燃料として飛ぶよ
うに売れる社会状況があったこと等。