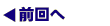 |
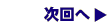 |
樹木医からの一言(8)
樹木治療における考え方
1. 樹木はその与えられた環境に適応し、常に最適な状態に
しようと樹形を作っているので、樹形を丹念に読み解く
ことにより樹木の健康状態や考え方を知ることができる。
2. 樹勢の維持回復にはエネルギーが必要であり、そのエネル
ギーは葉や枝における光合成によりつくられる糖に依存
している。
3. 樹木には無駄な枝葉は一つもない。
4. 腐朽部は、すでに材質腐朽菌が食べ尽くした後であり、
そこを取り除いても腐朽防止の点からは意味がない。
5. まだ固い変色部分は材質腐朽菌が最も活動している部分
だが、そこを削り過ぎるとシャイゴ博士らのいう防御層
あるいは障壁帯を傷つける危険性がある。
6. 幹の空洞化は材質腐朽菌とシロアリ・アリなどの昆虫に
より、材が食べ尽くされた部分であるが、空洞化してい
るということは、障壁帯(壁4)が完成していることを
示す。
7. 樹幹の切断部分に雨水進入防止の鉄板を被せることや、
モルタルや硬質ウレタンを塗布することは、腐朽防止の
観点から意味がない。
8. 雨水が溜まったウロは、材質腐朽が進行することはない。
かえって水を抜くことにより、防御層を破壊し健全部を
傷つけることになる。ウロに水が溜まるということは、
腐朽部と健全部が完全に区画化され、水も漏らさぬ状態
であることを示す。水が溜まっていれば、材質腐朽菌は
酸欠のために活動ができない。
9. 腐朽部へのアリの侵入は空洞化を促進するが、アリは腐
朽菌糸を食べるので、材質腐朽はかえって遅れるか阻止
される。アリが健全な材を食害するという事例は日本で
は報告されていない。
10. 栄養液の樹幹注入は、材質腐朽や胴枯れ性病害の発生を
促すことがあり要注意。樹幹注入後は必ず材の変色が生
じる。
11. 堆肥のマルチングは即効的な樹勢回復策であるが、同時
に深くまで根が入ることのできるような土壌改良と併用
すること。マルチングだけでは吸収根が地表近くに集中
し過ぎ、乾燥害を助長することがある。
12. 発根促進には堆肥が最も効果的である。