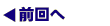 |
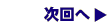 |
樹木医からの一言(7)
土壌生物
土壌生物は、土壌微生物と土壌動物に分けられる。土壌微生物として、細菌(バクテリア)とカビ(糸状菌)があげられるが、さらに原生生物を微生物に 含める場合がある。土壌の物質循環は、基本的に微生物によって担われている。
細菌は最も起源の古い生物で、核が膜で囲まれていない原核生物である。栄養の取り方が様々であり、無機栄養と有機栄養とを含む。細菌は土壌動物の体 内や排泄物中では活発な活動を行なっている。多くの細菌は従属栄養生物であり、土壌では植物の枯死体や根からの有機物、動物の死体や分泌物などを利用している。
カビは細菌よりも酸性の環境により強く、森林土壌で優先している。カビは真核生物で、細胞が長くつながった糸状の菌糸を伸ばし、途中で枝分かれし た先端などに、分生胞子を作る。カビの中には腐生性のものから植物や動物の寄生性、そして菌根菌とよばれる共生性のものが含まれている。
土壌動物とは土壌に生息する動物すべてを指す。体の幅が0.1ミリメートル程度より小さい微小な動物は、小型土壌動物とよばれ、土壌の液相の部分に生 息している。体が小さいので、水膜に体を浸している。原生動物や線虫などである。多くは土壌水中の溶存有機物や細菌、カビ、藻類を摂食している。
2ミリメートルまでの体幅の動物は中型土壌動物とよばれ、トビムシやダニ類などの小型の節足動物が多い。土壌中の孔隙を移動することができる。ト ビムシは生息場所のまわりの有機物を区別せずに食べることが知られているが、土壌表層ではカビや藻類を選択的に食べている。
2ミリメートルよりも体幅が大きくなると、土壌に自分で孔を掘らないと移動できなくなる。ミミズやヤスデ、ダンゴムシの仲間を大型土壌動物とよぶ。 土壌表層の落葉層は間隙が多いので、落葉層にすむ大型土壌動物が多い。ミミズは、落葉、腐植、土壌を食べ、現存量の多い土壌動物である。ムカデは一 般に捕食性であるが、ヤスデは落葉や腐植、そして土壌を食べる。
さらにモグラやネズミなど、土壌に生活する脊椎動物はこれまでみてきた無脊椎動物に比べると格段に体が大きいので、巨大土壌動物とよぶ場合もある。 ミミズなどの重要な捕食者であり、腐食連鎖と捕食関係でつながっている。