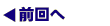 |
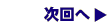
|
樹木医からの一言(6)
土壌とは…
土壌とは、岩石が下界の影響によって物理的あるいは化学的な風化作用を受け、それに動物や植物の遺体が加わり、さらにその遺体が土壌生物の作用を受けて互いに混じり合い、一体となり、その与えられた環境で安定した状態(平衡状態)に移りつつあるか、平衡状態に達した自然物である。単なる岩石が細かくなったものではなく、無機物と有機物の複合であり、様々な層構造を持つ。
森林土壌では地表面を覆う有機物層があり、多くの異なった植物が同じ場所に共存している。土壌の表層に分解の進んでいない落葉の層がありL層(落葉層)とよぶ。その下に分解のより進んだ有機物層があるが、これは分解程度によってF層(粗腐植層)、とH層(腐植層)に分けることができる。有機物は土壌の表層で比較的多く混入しており(A層)、混入の少ないB層と分けることができる。B層の下部には岩石が風化して粒子となったC層があり、その下には岩石がある(R層)。有機物層からは腐植酸などが移動して土壌で粘土鉱物に吸着され、より安定な有機物として存在する。
土壌は植物に必要な栄養塩類をどのように蓄えているのだろうか。土壌はイオン交換体であり、イオンの形で土壌水に溶解した元素や化合物を保持したり、交換したりする。この土壌の持つイオン交換能が土壌を植物栄養の場としている。植物に必要な必須元素はほとんどがイオンの形で根から取り込まれる。土壌が溶液中のイオンを吸着するためには、土壌の粒子が電気的に荷電していなくてはならない。土壌の陰荷電は粘土鉱物や腐植によって担われている。したがって、非常に風化が進んだ土壌を除いて通常土壌表面は全体として負に荷電している。また、腐植も負の荷電を持つので、土壌では陰イオンの吸着に比べて陽イオンの吸着サイトが多い。
土壌は鉱物や有機物がただ漫然と集まったものではなく、複雑な構造を持っている。土壌は鉱物などの固体以外に液体(土壌水)、気体(土壌中の隙間)からなっている。土壌孔隙は土壌のかなりの部分を占める。
また土壌では二酸化炭素濃度が高く、酸素濃度が低い。これは植物は根でも呼吸をしており、他の従属栄養生物とともに酸素を消費するからである。