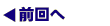 |
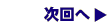 |
樹木医からの一言(5)
根系について
根は植物の地上部を支え、水分や養分を吸収する機能を持つものとして発達してきた地下器官であり、地下部全体を根系という。根系をなす部分はいくつかに分けられる。幹と根の接続部分を根株といい、太い塊状をなし、根系全体の重量の約半分を占める。根系の骨格をなす太い根を主根といい、垂直に伸びる直根、水平方向に発達する側根、両者の中間的な心根に分けられる。
また、主根から分岐したやや太い根を副根という。副根からさらに分岐したひげ根や白根を細根といい、水分や養分の吸収をつかさどるので吸収根ともいう。ただし、吸収根として機能できるのは短い場合は数日、長くても十数日とごく限られており、生育期間中は常に新しい吸収根を発生させ続けると同時に、多くの根を枯死させている。先端には根冠と呼ばれる保護組織があり、伸長する根と土壌粒子との摩擦を防いでいる。
根系は樹種によって特有な形があるが、直根のとくに発達するものは、深根性樹種(マツ・モミ等)と呼ばれ、直根の発達が悪いのが浅根性樹種(広葉樹に多い・ヒノキ・カラマツ等)である。
根の発達は、土壌の性質、特に土壌層が浅いか深いか、硬いか柔らかいか、土壌水分、水位の高低などに影響を受けるが、根の主要な分布域は表層土壌であって、地表下三〇〜四〇cmに全根量の約80%が分布する。根の発達は地上部のそれと平衡的であり、地上部(T)と地下部(R)の重量比(T/R比)は通常3程度である。なお、根には空中の枝や幹から、また地中の根から空気中に出るものもあり、気根という。枝から垂下するもの、幹から出た蛸足状の支柱根や、板状に発達した板根など形態は様々である。
地上部(幹・枝葉)の総重量3トンの樹木の場合、根系の総重量は1トンであり、そのうち根株が半トン、根株以外の根系の合計が半トンということになりますが、現場に詳しい皆さん、如何でしょうか。尤も自然樹形を保っている樹木の場合には該当するでしょうが、強剪定された樹木(例えば街路樹等)には、少し無理があると思います。