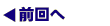 |
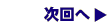 |
樹木医からの一言(4)
地球温暖化と低炭素社会
近年、気候が急激に変化している。この変化は人為的な温室効果ガスによるものであることはほぼ間違いなかろう。このような状態がずっと続けば、人類の生存基盤である地球環境に多大の影響を与えることは明白である。
今後、人類が引き続き化石燃料に依存しつつ、高い経済成長を目指すならば、今世紀末には、地球の平均気温の上昇は、4度に達すると予測されている。そうなれば、地球上の各地の生態系は、こうした急激な変化に対処することが出来ず、死滅の道を歩むことになる。動物は北上することも出来ようが、植物は移動出来ないから尚更大変である。
なぜこうした事態が起こってしまったのか。それは二酸化炭素の排出量が自然の吸収量を大きく超えているためである。人類が化石燃料の消費によって毎年排出する二酸化炭素の量は約70億炭素トンであり、今後さらに増加すると予測されている。一方自然界が1年間に吸収できる二酸化炭素の量には限りがあり、人為的な排出量のうち約30億炭素トンにとどまると推定されている。
気候を安定させて悪影響の拡大を防ぐには、人類全体が排出する温室効果ガスの量と吸収量のバランスをはかる必要があろう。
途上国と比べると、数倍の排出量を行っている日本を含む先進国は、今後次世代の未来を損なわないために、「低炭素社会」の実現にむけて早急に行動を起こすことが求められている。
私たちも他人事ではないが、もともと二酸化炭素が98パーセントの原始大気に酸素を提供したのは植物。酸素とともに出来たのが光合成生成物、いわゆる現植物体、その集合体として森林等、古の風化したものとして化石燃料、要するに燃えるものすべてであろう。つまり、燃えるものすべてを燃やすと、地球上から酸素がなくなるということになる。
今のように森林を伐採して、化石燃料を消費すればどうなるか、結果は見えている。恐竜でさえ1億数千万年栄えた歴史があるなかで、高等動物であるはずの人間が、わずか300〜500万年の歴史の幕を閉じようとしているのは言い過ぎであろうか。