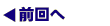 |
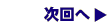 |
樹木医からの一言(15)
「マツ枯れ」について その7
・ マツノザイセンチュウもニセマツノザイセンチュウも、植
物のカルス細胞でよく増殖する。
・ マツノザイセンチュウは、マツ類以外にモミ類やトウヒ類、
カラマツ類、ヒマラヤスギにも感染する。ヒマラヤスギは、
マツ科の植物である。
・ 罹病木の最初の病徴として、樹脂分泌が減退ないし停止す
ることが知られている。
・ マツノザイセンチュウが寄生マツの樹体内に侵入するのは
若い枝からであり、侵入後の主な移動経路は樹皮部に分布す
る樹脂道である。
・ 細胞同士の隙間にできたトンネル状の構造で、その周囲を
エピセリウム細胞という分泌細胞が取り囲んでいる。この細
胞壁は薄く、マツノザイセンチュウが移動した部位ではこの
細胞が破壊され、他の柔細胞にも変性や壊死が起こる。
・ やがて初期の樹脂浸出異常やエチレン生成はおさまり、外
見的には病徴の進展が停止しているように見える時期が続く
が、この時期に過敏感反応が静かに進行し、植物の色素や苦
味成分、あるいは防御物質として知られているポリフェノー
ルなどの異常代謝産物が生成され柔細胞中に蓄積し、やがて
細胞は壊死し、その内容物が細胞外に放出される。
・ 細胞内容物が漏出し、水分通導の場である仮導管を次第に
閉塞したり、その仮導管に気泡が詰まる「キャビテーション」
を起こしたりするようになる。やがて完全に水が樹冠に供給
されなくなり、マツ類は萎凋・枯死する。
・ ポリフェノール性物質のタンニン含有量は、線虫類の増加
に対抗するように、前もって増加している。その量が減少す
ると初めて線虫数の急増が見られる。
・ 線虫に感染したアカマツやクロマツの組織で活性酸素が発
生する。細菌などの異物が侵入したとき、その強力な酸化作
用で異物を殺菌する直接的な働きと、それに続く抵抗反応を
導くためのシグナルとしての働きの両面がある。
・ 生物は長い進化の歴史の中で、細胞内の活性酸素濃度を低
く抑えるように様々な仕組みを獲得してきた。活性酸素を消
去する一連の「スカベンジャー(掃除屋)」と呼ばれる分子
群がそれである。ポリフェノールの一種であるタンニンにも、
この機能がある。